毎度定型文ですが、本文はGoogle Gemini pro2.5 Deep Researchにて生成した内容です😋
ご興味ある方は、出典付きですがハルシネーションの可能性も踏まえ、批判的吟味しながらご覧ください!
序論:二つの指針と二分された国家
2010年9月1日、日本の医学界に衝撃が走った。日本脂質栄養学会が「長寿のためのコレステロールガイドライン 2010年版」を発表したのである 1。この文書は、既存の医学的定説に対する単なる更新や修正ではなく、数十年にわたり築き上げられてきた治療パラダイムそのものへの根本的な挑戦状であった。
このガイドラインが投じた波紋の中心には、メディアの注目を集めた扇動的な主張があった。「元気で長生き」という目標のためには、総コレステロール(TC)やLDLコレステロール(LDL-C)の値は、むしろ高い方が長寿につながるというのである 3。これは、心血管疾患予防の国際的な常識である「コレステロールは低い方が良い(the lower, the better)」という考え方を真っ向から否定するものであった。
この挑戦に対し、医学界の中枢からの反応は迅速かつ強硬であった。日本動脈硬化学会は2010年10月14日、「科学的根拠なく、必要な患者の治療を否定する」として、この長寿ガイドラインを「断じて容認することはできない」とする声明を発表した 1。さらにその一週間後、10月20日には、日本医師会、日本医学会、そして日本動脈硬化学会の三者が合同で記者会見を開くという異例の事態に発展した。席上、日本医師会長および日本医学会長は、長寿ガイドラインを「学問的に考えても無茶な理論」であり、「国民を誤った方へ導くもので、大変危険」だと厳しく断じた 5。
この学術的な論争は、象牙の塔の中にとどまらなかった。報道を通じて拡散された「コレステロールは高い方が長生きする」というメッセージは、患者やその家族の間に深刻な混乱を引き起こした。高リスクの家族性高コレステロール血症患者が自己判断で生命維持に不可欠な服薬を中止する事例も報告されるなど、この論争は現実世界の公衆衛生上の危機へと発展したのである 6。本報告書は、この2010年のコレステロール論争を、単なる科学的対立としてではなく、日本の公衆衛生を揺るがした重大な事象として捉え、その全貌を深層から分析するものである。
論争の核心を理解するため、まず対立する二つのガイドラインの根本的な違いを概観する。
表1:2010年長寿ガイドラインと2007年動脈硬化予防ガイドラインの比較
| 項目 | 長寿のためのコレステロールガイドライン(2010年版) | 動脈硬化性疾患予防ガイドライン(2007年版) |
| 提唱団体 | 日本脂質栄養学会 | 日本動脈硬化学会 |
| 主要目標 | 「元気で長生き」の実現(総死亡率の最小化) 3 | 動脈硬化性疾患(心筋梗塞、脳梗塞など)の予防 3 |
| 主要評価指標 | 総コレステロール(TC) 2 | LDLコレステロール(LDL-C) 7 |
| 核心的主張 | コレステロール値が高い方が長寿である 3 | リスクに応じてLDL-C値を低く管理する方が疾患予防に繋がる 9 |
| 提唱する「至適」値 | 総死亡率が最も低いTC値は 240−259 mg/dL 2 | リスクに応じてLDL-C目標値は <160 mg/dL から <100 mg/dL 8 |
| 主要な根拠 | 日本人を対象とした観察コホート研究のメタアナリシス 2 | **ランダム化比較試験(RCT)**を頂点とする国際的なエビデンス全体 4 |
第I部:「長寿のためのコレステロールガイドライン」(2010年)― 挑戦者のマニフェスト
このセクションでは、まず論争の火種となった長寿ガイドラインの主張を客観的に提示し、その哲学、具体的な提言、そして根拠とされたエビデンスを詳細に分析する。
1.1. コア哲学:「元気で長生き」への目標転換
長寿ガイドラインの根底には、健康の定義そのものを問い直すという哲学的な転換がある。それは、治療のゴールを「動脈硬化性疾患」という特定の病態の予防から、「総死亡率の低下」、すなわち「元気で長生き」という、より包括的で全体的な目標へとシフトさせることである 3。
この視点に立てば、動脈硬化学会のガイドラインは、その目的が動脈硬化性疾患の予防に限定されており、視野が狭すぎると批判される。ある治療法(例えばコレステロール低下療法)が特定の疾患のリスクを下げたとしても、それが他の原因による死亡リスク(例えばがんや感染症)を増加させ、結果として総死亡率を改善しない、あるいは悪化させる可能性があるのであれば、その治療の価値は根本から疑われるべきである。長寿ガイドラインの提唱者たちは、治療の真の価値は、特定の疾患経路への影響ではなく、最終的な寿命全体への影響によって判断されなければならないと主張した。
1.2. 主要な主張と提言
この哲学に基づき、長寿ガイドラインはいくつかの具体的な主張を展開した。
- 中心的主張: 最も核心的な主張は、日本人集団においては、総コレステロール(TC)およびLDLコレステロール(LDL-C)の値が高いほど、総死亡率が低いという相関関係が存在するというものである。ガイドラインは、日本人を対象とした複数の疫学調査を統合した結果、総死亡率が最も低くなるのはTC値が 240−259 mg/dL の範囲にある人々であると結論づけた 2。これは、従来の基準値(例えばTC
220 mg/dL 以上を高脂血症とする)を大幅に上回る値であり、従来の治療目標とは正反対の方向性を示すものであった。 - 食事性コレステロールに関する見解: 長寿ガイドラインは、当時の一般的な食事指導にも異議を唱えた。食事からのコレステロール摂取量を増やしても、血清コレステロール値の長期的な上昇にはつながらないと主張した。摂取後の短期的な(週単位での)上昇は認められるものの、生体の恒常性維持機能により、長期的には安定するという見解である 12。これは、コレステロールを多く含む食品(卵など)の摂取を制限する従来の栄養指導の根拠を揺るがすものであった。
1.3. エビデンスの基盤:日本人コホート研究のメタアナリシス
長寿ガイドラインがその大胆な主張の根拠としたのは、日本人を対象とした観察コホート研究のメタアナリシス(複数の研究結果を統計的に統合する手法)であった。彼らの反論文書によれば、その方法論にはいくつかの特徴的な選択が見られる 2。
- データ選択: 日本国内で発表された、総コレステロールと総死亡率の関連を調査した論文を可能な限り収集した。食生活の変化を考慮し、1995年以前に発表された古い論文は除外された。さらに、5000人以上を5年以上追跡したという基準を適用し、最終的に9報の研究が解析対象となった 2。
- 「地方誌」の論文の採用: 最も物議を醸した点の一つが、査読(専門家による論文審査)を経ていないか、あるいは学術的評価が必ずしも高くないとされる「地方誌」に掲載された論文を意図的に解析に含めたことである。この決定について、著者らは二つの理由を挙げている。第一に、これらの論文が執筆された当時は「コレステロールは高いほど危険」という認識が主流であったため、逆に「高い方が死亡率が低い」という結果は予期せぬ発見として報告されており、結果を知っていることによるバイアス(先入観)が入り込みにくかったはずだという点。第二に、地方誌の著者らは製薬企業との利益相反(COI)問題が基本的に存在しなかったはずであり、より中立的なデータである可能性が高いという点である 2。
- 主要評価項目としての「総死亡率」: 長寿ガイドラインが最終的な評価指標として「総死亡率」を絶対視したことは、その論理構成において極めて重要な意味を持つ。特定の死因(例えば心疾患死)ではなく、あらゆる原因による死亡を合算した総死亡率こそが、コレステロール値が健康全体に与える正と負の影響を総合的に評価できる唯一の指標であると彼らは主張した 2。この評価項目の選択は、単なる哲学的な違いにとどまらない。観察研究においては、コレステロール値と総死亡率の関係は、しばしばU字型またはJ字型の曲線を描くことが知られている。つまり、非常に高い値だけでなく、非常に低い値でも死亡リスクが上昇する現象が見られる。この曲線の底、すなわち死亡率が最も低くなる点(長寿ガイドラインではTC
240−259 mg/dL)を「至適」と定義することにより、彼らは自らの主張を構築した。この戦略は、低値側でのリスク上昇の主要因である「逆の因果関係」(後述)の問題を意図的に軽視し、ランダム化比較試験(RCT)で確立されたLDL-Cと動脈硬化性疾患との因果関係から目を逸らすことを可能にする、極めて巧みな論理的選択であった。
1.4. 既存定説への批判:欠陥のある臨床試験と製薬企業の影響
長寿ガイドラインの提唱者たちは、守勢に立つだけでなく、既存の医学的コンセンサスに対しても攻撃的な批判を展開した。
- 利益相反(COI)の問題: 彼らは、米国コレステロール教育プログラム(NCEP)のガイドラインや、それに追随する日本の動脈硬化学会ガイドラインが、製薬企業の資金提供によって著しく歪められていると強く非難した。ガイドライン作成委員の多くがスタチン(コレステロール低下薬)メーカーから多額の金銭的支援を受けている事実を指摘し、その結果として推奨される基準値や治療方針の信頼性に疑問を呈した 2。
- 臨床試験の解釈への疑義: さらに、近年の大規模な介入試験の結果を詳細に見れば、「低い方が良い」という仮説はもはや支持されないと主張した。特に、臨床試験の透明性を高めるEUの新法が2004年に施行されて以降、コレステロール低下療法の有効性を示せない、あるいは有害性を示唆する試験結果が次々と報告されていると指摘した。具体例として、ASPEN、CORONA、ENHANCE、SEASといった試験名を挙げ、これらの結果はコレステロール原因説を否定するものだと論じた 2。また、日本人を対象とした大規模試験であるMEGAスタディについても、試験途中のプロトコル変更や統計的な不自然さを理由に「極めて疑わしい」と断じた 2。
この一連の主張の背後には、「エビデンスのナショナリズム」とも呼べる戦略が見て取れる。彼らが日本人データに固執し 2、国際的なエビデンスを「日本人には当てはまらない」として退ける態度は、二重の目的を果たしている。第一に、LDL低下療法の有効性を圧倒的に支持する膨大なグローバルデータを議論の対象外とすることを可能にする。第二に、査読を経ていないものを含む国内の観察研究に基づいた自らのメタアナリシスの価値を相対的に高めることができる。この戦略は、彼らの結論を、現代心臓病学の根幹をなす国際的なエビデンスによる反論から守るための、一種の防御壁として機能したのである。
第II部:確立されたコンセンサス―「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」(2007年)
長寿ガイドラインが覆そうとした既存の定説とはどのようなものであったか。ここでは、論争の背景を理解するために不可欠な、日本動脈硬化学会による2007年版のガイドラインの内容を詳述する。
2.1. 基本原則:リスク層別化とLDL-Cの最重要視
2007年版ガイドラインは、日本の脂質管理における重要な進化を示した。それは、管理の主要ターゲットを従来の総コレステロール(TC)から、動脈硬化を引き起こす主犯とされるLDLコレステロール(LDL-C)へと明確に移行させた点である 7。これは、LDL-Cがアテローム性動脈硬化の中心的役割を担うという国際的な科学的コンセンサスに沿ったものであった。
さらに、このガイドラインの核心的な原則は、単一のコレステロール値で治療方針を決定するのではなく、個々人が持つ動脈硬化性疾患発症の絶対リスクに基づいて管理目標を設定する「リスク層別化」の導入である。この絶対リスクは、主要な危険因子をいくつ有するかによって評価される 8。
ガイドラインで採用された主要危険因子は以下の通りである 8:
- 加齢(男性45歳以上、女性55歳以上)
- 高血圧
- 糖尿病(耐糖能異常を含む)
- 喫煙
- 冠動脈疾患の家族歴
- 低HDLコレステロール血症(HDL-C値が 40 mg/dL 未満)
2.2. 診断基準とリスク別管理目標値
2007年版ガイドラインは、まず「高脂血症」という病名を、HDL-Cが低い状態も問題視する観点から「脂質異常症」へと変更した 7。その上で、具体的な診断基準とリスク別の管理目標値を定めた。
- 脂質異常症の診断基準(空腹時採血):
- 高LDLコレステロール血症:LDL−C≥140 mg/dL
- 低HDLコレステロール血症:HDL−C<40 mg/dL
- 高トリグリセライド血症:トリグリセライド ≥150 mg/dL
重要なのは、この診断基準が直ちに薬物療法の開始を意味するものではないと明記されている点である 9。
- リスク層別化とLDL-C管理目標値: 薬物療法を考慮するか否か、またどのレベルまでLDL-Cを下げるべきかは、以下のリスク区分に応じて決定される。この個別化されたアプローチは、長寿ガイドラインの画一的な推奨とは対照的である。
表2:リスク層別化とLDL-C管理目標値(動脈硬化性疾患予防ガイドライン, 2007年版)
| 予防区分 | リスク区分 | LDL-C以外の主要危険因子数 | LDL-C管理目標値 (mg/dL) |
| 一次予防 (まず生活習慣の改善を行い、薬物療法を考慮) | カテゴリーI(低リスク群) | 0個 | <160 |
| カテゴリーII(中リスク群) | 1~2個 | <140 | |
| カテゴリーIII(高リスク群) | 3個以上 | <120 | |
| 二次予防 (生活習慣の改善と共に薬物療法を考慮) | 冠動脈疾患の既往あり | ― | <100 |
出典: 8
注:糖尿病、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症の既往がある患者は、他の危険因子の数にかかわらず、自動的にカテゴリーIII(高リスク群)として扱われる 10。
2.3. 科学的エビデンスの階層性
2007年版ガイドラインの科学的哲学は、長寿ガイドラインとは根本的に異なる。それは、利用可能なエビデンスをその質によって階層化し、最も信頼性の高いものを重視するという考え方に基づいている。
医学研究において、ある介入(例:LDL-C低下薬の投与)と結果(例:心筋梗塞の予防)との間に因果関係を確立するためのゴールドスタンダード(最も信頼性の高い基準)は、大規模な**ランダム化比較試験(RCT)**であると広く認められている。RCTは、研究参加者を無作為に治療群と対照群(プラセボ群)に割り付けることで、未知の交絡因子(結果に影響を与えうる他の要因)の影響を最小限に抑え、介入そのものの効果を純粋に評価することができる。
動脈硬化学会のガイドラインは、日本国内および国際的な疫学的研究と臨床的エビデンスに基づいて策定されており 7、特にこのRCTの結果を重視している。これは、相関関係しか示せない観察研究に主たる根拠を置く長寿ガイドラインのアプローチとは、科学的方法論の根幹において一線を画すものである。
第III部:科学的十字架―論争のポイント別分析
本セクションでは、両者の主張を直接対決させ、確立された疫学および臨床研究の原則に照らして、その妥当性を分析する。
3.1. 方法論の根本的断絶:「相関」と「因果」、そして「逆の因果関係」
論争の最も核心的な対立点は、「相関関係」と「因果関係」の解釈にある。
- 医学界主流派の論理: 日本動脈硬化学会をはじめとする医学界主流派が長寿ガイドラインを批判する最大の論拠は、**「逆の因果関係(reverse causation)」**という概念である 4。彼らの主張はこうだ。観察研究で見られる「低コレステロールの人々で死亡率が高い」という現象は、低コレステロールが死を招いている(因果関係)のではなく、死につながるような重篤な疾患(例:がん、肝疾患、栄養不良など)が、結果としてコレステロール値を低下させている(逆の因果関係)というものである 1。コレステロールは肝臓で産生されるため、肝機能が低下する肝疾患では血清コレステロール値が低下することは医学的な常識である。
- 具体的な証拠: この仮説を裏付ける証拠として、動脈硬化学会は大規模コホート研究であるNIPPON DATA80の解析結果を挙げている。この研究では、低コレステロール血症で死亡率が高かった集団を詳しく分析したところ、肝疾患を持つ人の割合が有意に高かったことが明らかになった 1。これは、肝疾患という原因が、低コレステロール血症と高い死亡率という二つの結果を同時にもたらしたことを示唆しており、「逆の因果関係」の典型例であると彼らは説明する。
- 挑戦者の反論: これに対し、長寿ガイドラインの提唱者たちは、いくつかの要因を調整してもなお低コレステロール群での死亡率が高い傾向は残ると反論する。また、仮に疾患が低コレステロールの原因であったとしても、それは危険な状態を示すサインであり、「低い方が良い」という哲学の下でさらに値を下げたり、その状態を放置したりすべきではないと主張した 2。しかし、この反論は、因果関係の方向性という根本的な問題から巧みに論点をずらすものとなっている。
3.2. エビデンスの戦い:査読の価値 vs. 出版バイアスの問題
科学的知見の妥当性をめぐる両者の見解も、真っ向から対立した。
- 医学界主流派の批判: 動脈硬化学会は、長寿ガイドラインが査読を経ていない論文を根拠としている点を厳しく批判した。科学的妥当性を担保するための専門家による厳格な審査プロセスを経ていない文献に基づくメタアナリシスは、科学的信頼性が極めて低く、そのような文書を「ガイドライン」と呼ぶこと自体が容認できないと断じた 4。
- 挑戦者の弁護: 一方、長寿ガイドラインの提唱者たちは、査読誌から漏れた論文を意図的に含めたのは、既存の学術界に蔓延する二つのバイアスに対抗するためであったと弁護する。一つは、肯定的な結果が出た研究は論文として出版されやすいが、否定的・無効な結果に終わった研究は出版されにくいという**「出版バイアス(publication bias)」。もう一つは、製薬企業からの資金提供を受けた研究が、その企業の製品に有利な結果を導きやすいという「利益相反(COI)」**の問題である 2。この対立は、伝統的な科学的検証プロセス(査読)の重要性を訴える側と、そのプロセス自体が歪んでいると主張し、より広範で(彼らが言うところの)バイアスのないデータセットを構築しようと試みる側との、科学哲学における根本的な衝突を浮き彫りにした。
3.3. 臨床試験の解釈:スタチンは有効か?
大規模臨床試験の結果をめぐる解釈も、両者で劇的に異なっていた。
- 非対称な解釈: 動脈硬化学会が個々の試験結果を、すべての利用可能なエビデンスを統合したメタアナリシスの文脈の中で評価するのに対し、長寿ガイドラインの提唱者たちは、自らの主張に合致するように見える特定の試験結果や、試験全体の結論とは異なるサブグループ解析の結果を「つまみ食い」する傾向が見られた。
表3:コレステロール論争で引用された主要臨床試験の解釈
| 試験名 | 主要な結果(中立的要約) | 動脈硬化学会の解釈(コンセンサス) | 脂質栄養学会の解釈(挑戦者) |
| MEGA | 日本人一次予防において、プラバスタチンは食事療法単独に比べ冠動脈疾患リスクを有意に低下させた。 | 日本人におけるスタチン一次予防の有効性を示す重要なエビデンス。 | 試験途中のプロトコル変更や統計的異常があり「極めて疑わしい」 2。 |
| ENHANCE | エゼチミブとシンバスタチンの併用は、シンバスタチン単独よりLDL-Cを低下させたが、頸動脈内膜中膜厚の進展を抑制しなかった。 | 代理エンドポイント(頸動脈肥厚)の試験であり、心血管イベントを評価したものではない。結果の解釈には慎重を要する。 | LDL-Cをさらに低下させても動脈硬化進展に影響しない証拠であり、コレステロール仮説を否定する 2。 |
| SEAS | エゼチミブとシンバスタチンの併用は、大動脈弁狭窄症の進行に影響せず、がんの発生が有意に増加した。 | 特定の病態(大動脈弁狭窄症)に対する試験であり、一般的な脂質異常症患者に外挿できない。がんリスクについては他の多数の試験で否定されている。 | コレステロール低下療法が無効であるだけでなく、有害(がんリスク増)である可能性を示す証拠 2。 |
| CORONA / GISSI-HF | 慢性心不全患者において、ロスバスタチンは心血管イベントを減らさなかった。 | 心不全という末期的な病態では、アテローム硬化の進展抑制がもはや予後に寄与しない可能性を示唆。スタチンが全ての心疾患に有効なわけではない。 | 高齢者や心不全患者においてコレステロール低下療法が無効であることを示す証拠 2。 |
| J-LIT | 日本人高コレステロール血症患者6年間の追跡調査。スタチン投与後のTC低値群で、がん死亡率・総死亡率が高かった。 | 観察研究であり因果関係は不明。「逆の因果関係」の可能性が高い。 | スタチン投与によってコレステロールを下げすぎると、がん死亡や総死亡が増加するという直接的な証拠 2。 |
この表は、同じデータがいかに異なる物語を語るために利用されうるかを示している。コンセンサス側はエビデンスの全体像と階層性(RCT > 観察研究)を重視するのに対し、挑戦者側は自らの仮説を補強する個別のデータ片を強調する戦略をとった。
3.4. 利益相反:正当な懸念か、論点逸らしの戦術か
長寿ガイドラインの提唱者たちが繰り返し指摘した、主流派ガイドライン作成における利益相反(COI)の問題は、この論争のもう一つの重要な側面である。
- 告発の内容: 彼らは、動脈硬化学会のガイドライン作成に関与した専門家の多くが製薬企業から多額の寄付金や報酬を得ており、その金銭的関係がガイドラインの中立性を損なっていると強く主張した 2。
- 文脈の理解: 医学研究におけるCOIが深刻かつ現実的な問題であることは、広く認識されている。ガイドライン作成者と企業との間に金銭的なつながりが存在すること自体は、事実である。
しかし、この論争におけるCOIの使われ方には、注目すべき非対称性が見られる。長寿ガイドライン側は、COIを主流派の科学的結論そのものを無効化するための主要な攻撃手段として用いた 2。一方、動脈硬化学会側は、自らの反論において、COIの問題にほとんど言及せず、一貫して長寿ガイドラインの科学的・方法論的な欠陥(逆の因果関係、査読の欠如、データの誤解釈など)を論じることに終始した 1。
この非対称性は、両者の立脚点の違いを物語っている。主流派は、科学的エビデンスが非常に強固であるため、資金源がどうであれ、その結論は揺るがないという姿勢をとる。対照的に、挑戦者側は、自らの科学的基盤が脆弱(観察研究に依存し、逆の因果関係を無視)であるため、相手の信頼性そのものを攻撃し、研究エコシステム全体への不信感を煽る必要があった。COIという正当な懸念は、ここでは自らの方法論的弱点から注意をそらし、相手の土俵そのものを破壊するための強力なレトリックとして機能したのである。
結論:コレステロールの迷宮を抜けて―統合的考察と永続的影響
2010年のコレステロール論争を総括すると、それは本質的に二つの和解不可能なアプローチの衝突であった。一方は、地域的な観察データに対する包括的だが方法論的に欠陥のある解釈に基づき(長寿ガイドライン)、もう一方は、疾患特異的だが因果関係において強固な、国際的なエビデンスの階層性に基づく解釈(動脈硬化予防ガイドライン)であった。
長寿ガイドラインが、利益相反の問題や、治療の評価において総死亡率のような包括的な指標を考慮する必要性など、医学界が真摯に受け止めるべき重要な問題を提起したことは事実である。しかし、その核心的主張である「コレステロールは高い方が長生きする」という結論は、利用可能な最良の科学的エビデンスによる厳密かつ包括的な評価によって支持されるものではない。個人のリスクに応じた層別化と、LDLコレステロールを主要な管理目標とする動脈硬化性疾患の予防戦略は、依然として圧倒的な国際的科学・医学コンセンサスであり続けている。
この論争が残した最も重要な教訓は、学術的な議論が社会に与える影響の大きさにある。一つのガイドラインの発表が、科学的な反論を呼び、最終的には一般市民の間に深刻な混乱と健康被害をもたらした。メディアによって増幅された「コレステロールは体に良い」というセンセーショナルなメッセージは、患者の自己判断による服薬中断という危険な行動を誘発した 5。この一連の出来事は、科学的な論争が学界の中だけで完結するのではなく、現実世界に甚大な、時には致命的な結果をもたらしうることを示している。それは、研究者、医学会、そしてメディアが、複雑な健康情報をいかに慎重に、そして責任をもって伝えなければならないかという重い課題を突きつける。エビデンスに基づいた医療への国民の信頼が一度損なわれれば、その回復は容易ではなく、その代償は計り知れない。
最終的に、2010年のコレステロール論争は、専門家と市民の双方にとって、科学リテラシーの重要性を痛感させる出来事であった。相関関係と因果関係の違いを理解し、観察研究とランダム化比較試験といった医学的エビデンスの階層性を認識することは、複雑でしばしば矛盾に満ちた健康情報の中から真実を見抜くために不可欠なスキルである。この日本の事例は、その必要性を物語る、強力かつ永続的なケーススタディとして記憶されるべきであろう。
引用文献
- 「長寿のためのコレステロール ガイドライン2010 年版」に対する声明 – 日本医師会, 7月 31, 2025にアクセス、 https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20101020_1.pdf
- 日本動脈硬化学会 「長寿のための … – 日本脂質栄養学会, 7月 31, 2025にアクセス、 https://jsln.umin.jp/pdf/guideline/Hanron20101108c.pdf
- 長寿のためのコレステロールガイドライン(2010年版) – 医薬ビジランスセンター, 7月 31, 2025にアクセス、 https://npojip.org/contents/book/shohyo041_01.html
- 「長寿のためのコレステロール ガイドライン2010年版」に対する …, 7月 31, 2025にアクセス、 https://www.j-athero.org/jp/outline/20101014/
- 科学的根拠なし、『コレステロール高い方が長生き』ガイドラインに反対声明 | m3.com, 7月 31, 2025にアクセス、 https://www.m3.com/news/open/iryoishin/127193
- 日医白クマ通信(No.1341)定例記者会見「日本脂質栄養学会のガイドラインに異議」, 7月 31, 2025にアクセス、 https://www.med.or.jp/shirokuma/no1341.html
- 「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版」の概要と人間ドックでの活用 – J-Stage, 7月 31, 2025にアクセス、 https://www.jstage.jst.go.jp/article/ningendock2005/22/5/22_775/_article/-char/ja/
- 管理の指標におけるLDLコレステロールの重要性を全面に押し出す 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版」発行 | 生活習慣病の調査・統計, 7月 31, 2025にアクセス、 https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2007/003377.php
- 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007, 7月 31, 2025にアクセス、 http://www.mikinaika.com/advace/coresterol.html
- 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007 – 日本脈管学会, 7月 31, 2025にアクセス、 http://j-ca.org/wp/wp-content/uploads/2016/04/4810_5.pdf
- 今月の話題 対談:日本人の脂質管理のあり方を考える| トピックス – Therapeutic Research は, 7月 31, 2025にアクセス、 https://therres.jp/3topics/2010/20101112184737.php
- コレステロール ガイドライン – 日本脂質栄養学会, 7月 31, 2025にアクセス、 https://jsln.umin.jp/pdf/guideline/guideline-abstractPDF.pdf
- 1. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007 の“血清コレステロール値と動脈硬化性疾患, 7月 31, 2025にアクセス、 https://jsln.umin.jp/pdf/guideline/101213Kokaisitumon.pdf
- 一次予防と二次予防に分け、一次予防は危険因子の数に応じて管理目標を設定 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版」発行 – 日本生活習慣病予防協会, 7月 31, 2025にアクセス、 https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2007/003380.php
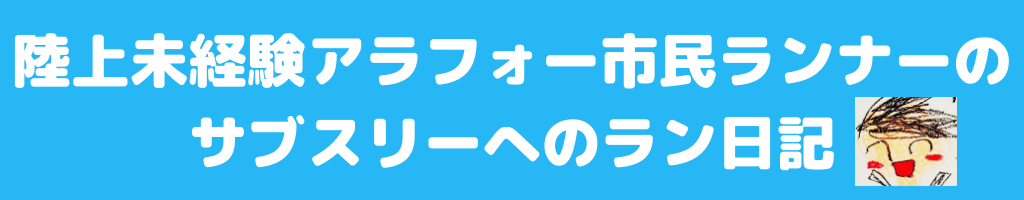
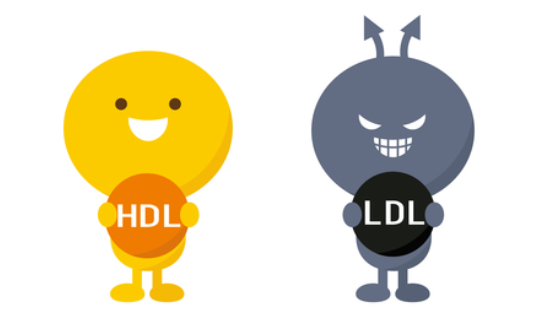
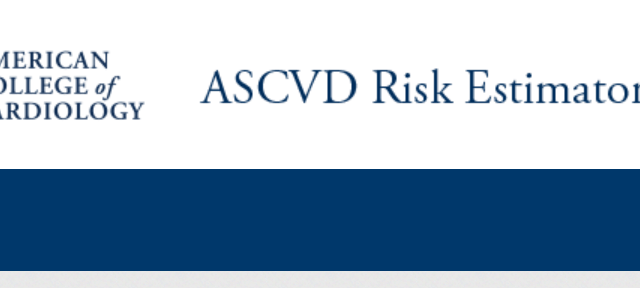
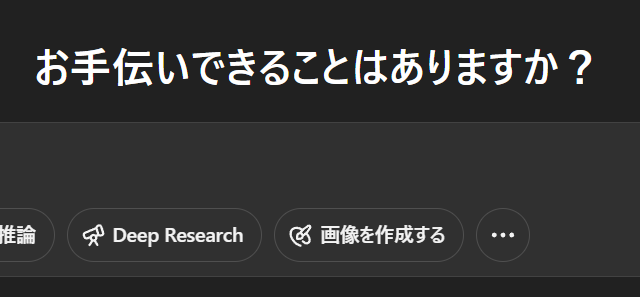

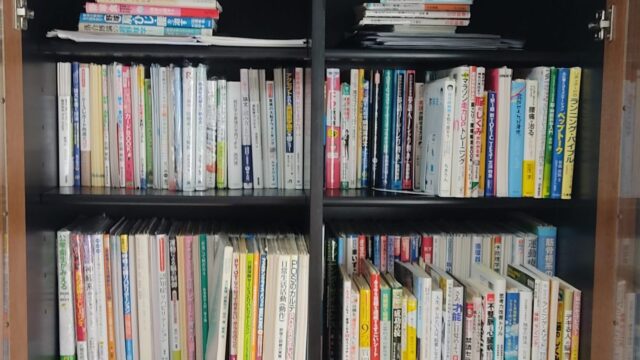
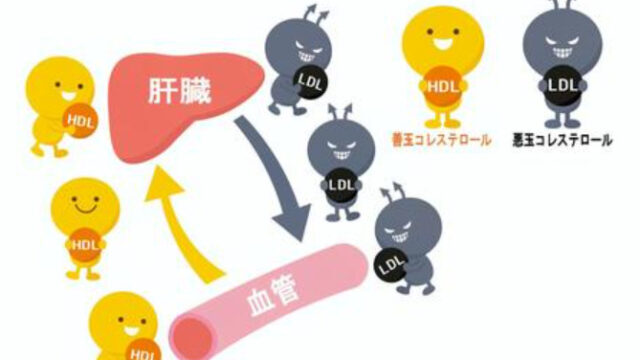
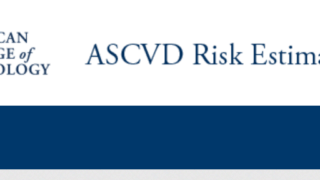





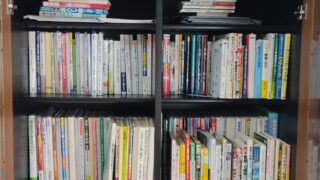

はじめまして。 とても興味をひかれました! ふだん改造ビーチサンダルやlun…
ありがとうございます。嬉しいです みちさんが保存療法でよくなることを願っています…
経過良好で安心しました^_^ やはりリハビリが大事なのですね。 術後の記事、…