毎度定型文ですが、本文はGoogle Gemini pro2.5 Deep Researchにて生成した内容です😋
ご興味ある方は、出典付きですがハルシネーションの可能性も踏まえ、批判的吟味しながらご覧ください!
測定の指令:「測定できないものは改善できない」という教義の脱構築
はじめに:測定という両刃の剣
現代の経営において、「測定できないものは改善できない」という警句ほど、広く浸透し、多大な影響力を持つ教義は他にないだろう。
この言葉は、データに基づいた意思決定の重要性を説く、シンプルかつ強力な指針として、あらゆる組織階層で受け入れられている。
しかし、本レポートは、この警句を単純な真実や偽りとしてではなく、その価値が適用方法に完全に依存し、安易な実践が組織に深刻な害をもたらしかねない、強力な概念として批判的に検証するものである。
本レポートの中心的な論点は、この原則がデータ駆動型の意思決定を重視する点で効果的なマネジメントの基礎となる一方で、その一般的な解釈は組織の現実を危険なほど単純化しすぎている、という点にある。
洗練されたアプローチとは、定量的指標と定性的理解のバランスを取り、測定の限界を認識し、そして皮肉にもこの言葉の発言者として誤って引用される思想家たち自身の警告に耳を傾けることである。
本レポートは、定量的指標の力を認めつつも、そのナイーブな適用がもたらす破壊的な結果を明らかにすることで、より全体的で持続可能な組織改善のための「インテリジェントな測定」のフレームワークを提示することを目的とする。
分析は、まずこの警句の物議を醸す起源を解き明かすことから始める。
そこには、経営文化の本質を物語る、根深い誤解の歴史が存在する。次に、測定が持つ正当な力と、それを実践するためのフレームワーク(KPI、PDCA、SMART)を探求する。
続いて、グッドハートの法則やW・エドワーズ・デミングの深遠な哲学をレンズとして、指標への固執がもたらす危険性を厳密に批判する。
最終的に、本レポートは、定量的洞察と定性的洞察を統合し、組織の全体的かつ持続的な改善を目指すための、統合されたフレームワークを提案する。
第1章 経営マントラの起源:誤解と誤用の物語
この章では、広く信じられているこの警句の歴史を丹念に解き明かし、その起源が見かけとは異なることを明らかにする。この「ルール」の土台そのものが、偉大な経営思想家たちの教えに対する根本的な誤解の上に築かれていることを示すことが、本章の目的である。
1.1 ドラッカー神話:根強く残る誤解
「測定できないものは改善できない(If you can’t measure it, you can’t improve it.)」あるいは「測定できないものは管理できない(You can’t manage what you can’t measure.)」という言葉は、数多くの文献やビジネスの現場で、「現代経営学の父」と称されるピーター・ドラッカーの言葉として確信をもって引用されている 1。この引用は、この警句に絶大な権威性を与えている。
しかしながら、より厳密な調査、特にドラッカーの著作や教えを保存・研究するドラッカー研究所のアーキビストによる徹底的な調査によれば、ドラッカーがこのフレーズやその一般的なバリエーションを執筆したり、公の場で述べたりしたという「証拠は一切ない」ことが判明している 8。これは、この言葉が持つとされる血統を根底から覆す、決定的な矛盾である。
この神話がこれほどまでに根強く残っているという事実は、経営の世界におけるシンプルで権威あるルールへの渇望を浮き彫りにしている。この警句をドラッカーに帰属させることで、本来であればそれ自体では持ち得ない知的権威を、単純化された思想に与える効果があったのである。
1.2 ドラッカーの真の哲学:「目標と『自己統制』による管理」
ドラッカーの思想の真髄は、「目標と自己統制による管理(Management by Objectives and Self Control)」、すなわちMBOにある 10。ここで極めて重要でありながら、しばしば見過ごされる要素が「自己統制(Self-Control)」である。
ドラッカーにとって、測定の目的はトップダウンによる管理統制のためではなく、個々の従業員が自らを管理する力を与えるためのものであった。目標とは、個人の貢献を組織の目的と一致させ、責任感と自律性を育むためのツールなのである 11。彼は、目標が明確で測定可能であるべきこと 15、そして評価と測定がマネジメントの重要な能力であること 17 を強調したが、それは常に、弱みを矯正するのではなく個人の強みを活かすことを優先する、人間中心の文脈の中に置かれていた 16。
ドラッカーの見解は、一般的に流布している警句よりもはるかにニュアンスに富んでいる。測定は、管理者にとっての鞭ではなく、働く個人にとっての道具なのである。広く知られた警句は、この自律性とエンパワーメントという本質的な文脈を剥ぎ取り、彼の哲学を純粋に機械論的なものへと歪めてしまっている。
1.3 デミングの皮肉:最も痛烈な批判者への帰属
この警句は、品質管理の父でありPDCAサイクルの提唱者としても知られるW・エドワーズ・デミングの言葉としても頻繁に引用される 22。彼の統計的プロセス制御(Statistical Process Control)への重点を考えれば、これはもっともらしく聞こえるかもしれない 25。
しかし、衝撃的なことに、デミングが実際に著書で述べた言葉は、その正反対である。「測定できなければ管理できないと考えるのは間違いである。それは高くつく神話だ(It is wrong to suppose that if you can’t measure it, you can’t manage it – a costly myth.)」 9。彼は一貫して、マネジメントにとって最も重要な数字は、しばしば「未知であり、知り得ない(unknown and unknowable)」ものであると警告していた 28。
これは単なる誤引用ではない。デミングの核心的哲学の完全な転倒である。彼の業績に対する最も深刻な誤解であり、警告として発せられた言葉が、規範的なルールへと変質してしまったのである。
1.4 デミングの深遠なる知識の体系:なぜ「目に見える数字」だけでは不十分なのか
デミングの哲学は、彼の「深遠なる知識の体系(System of Profound Knowledge)」に基づいている。これは、「システムへの理解」「ばらつきに関する知識」「知識についての理論」「心理学」という4つの相互に関連する要素から構成される 25。
彼は、数値目標や達成目標のみによる管理(彼が「5つの致命的な病」の一つとした)は、パフォーマンス低下の真の原因であるシステム的要因を無視するため、品質の低下と敵対的な人間関係を生むだけだと主張した 29。彼は、数値的なノルマや目標による管理を撤廃するよう提唱したのである。
デミングにとって、容易に測定できるものだけに焦点を当てることは、惨事を招く処方箋であった。それは、システム内の複雑な相互作用、働く人々の心理(例えば、「恐怖の排除」は彼の重要な原則の一つである)、そしてあらゆるプロセスに内在する統計的なばらつきを無視することに他ならない。効果的に管理するためには、単にアウトプットを数えるのではなく、システムを理解しなければならないのである。
ドラッカーとデミングという二人の巨匠への二重の誤引用は、単なる偶然ではなく、経営における根深いバイアスの兆候である。それは、ビジネス界に存在する、管理と予測可能性を約束するシンプルで機械論的なヒューリスティクスへの集団的な渇望を明らかにしている。その結果、彼らは自らの願望を最も尊敬する思想家に投影し、たとえそれが彼らの実際の教えを転倒させることになったとしても、その誤用に固執してきたのである。
この現象の背景には、経営文化がしばしば「思考」よりも「ツール」を優先するという事実がある。この警句は、深い思考を伴わずに適用できるツールとして機能する。一方で、ドラッカーやデミングの真の哲学は、思考様式の根本的な転換を要求する。したがって、この誤引用は一種の文化的な自己欺瞞であり、経営者たちが、より単純で、究極的には効果の薄い実践を行いながらも、巨匠たちの教えに従っているという感覚を抱くことを可能にしているのである。
第2章 測定の論理的根拠:直感から洞察へ
この章では、この原則が、その不確かな出自にもかかわらず、なぜこれほどまでに強く共感を呼び、核心的な真実を保持しているのか、その肯定的な側面を構築する。
2.1 「見える化」の原則:見えないものを可視化する
測定が持つ核心的な力は、抽象的な概念を可視化し、具体化する能力にある。これは日本の経営コンセプトである「見える化」そのものである 2。
例えば、ダイソンの掃除機に搭載されたLEDが目に見えないホコリを照らし出す技術や、内部統制監査で用いられる業務フローチャートやリスクコントロールマトリックスが複雑な業務プロセスを理解可能にする例が、この原則をよく示している 2。何かが見えるようになると、次に取るべき行動が明確になるのである。
測定はレンズのように機能し、「非効率だと思う」といった曖昧な感覚を、「プロセスAはプロセスBより30%時間がかかっている」といった具体的で観測可能なデータに変換する。この変換こそが、あらゆる合理的な改善努力の第一歩となる。
2.2 改善と客観的意思決定のためのベースライン設定
成功が定義され、追跡されなければ、成功しているかどうかを知ることはできない。ベースラインとなる指標がなければ、「改善」という主張は単なる推測に過ぎない 3。
測定は、主観的な直感を客観的な証拠に置き換えることで、データに基づいた意思決定を可能にする。これは、プロダクトマネジメントにおけるKPIの活用から、理学療法における筋活動の追跡まで、あらゆる分野で極めて重要である 1。
これこそが、この警句の論理的な核心である。「改善」とは相対的な用語であり、以前の状態からの変化を意味する。測定は、その状態を形式的に定義し、肯定的な変化が起こったことを検証する唯一の方法なのである。
2.3 組織の一体感、透明性、説明責任の醸成
測定結果をチームで共有することは、透明性を高め、組織の一体感(アライメント)を生み出す。誰もが目標を理解し、自らの仕事がそれにどう貢献するのかを把握できるようになる 1。
具体的な成功指標は、説明責任(アカウンタビリティ)を創出する。例えば、サービス提供者にとっては、それは「成功か失敗かの二者択一であり、中間はない」ことを意味し、専門用語の裏に隠れるのではなく、真の結果を出すことに集中せざるを得なくなる 3。また、投資家にとっては、成長に関する定量的データが意思決定の上で不可欠となる 35。
共有された指標は、共通の言語と共有された現実を創造する。これにより、パフォーマンスに関する議論が非人格化される。それは個人を非難することではなく、データを分析し、プロセスを改善することについての対話となるのである。
測定の分析的な力と同様に重要なのが、その心理的な力である。ある行動を測定するという行為そのものが、正式な分析や介入が行われる前に、その行動を望ましい方向へと変化させることが多い。この現象は、ある個人がアプリで日々の歩数を記録し始めたという逸話によって見事に示されている 4。その直接的な効果は、翌日にはその数値を改善したいという欲求であった。「活動レベルを測定するという行為そのものが、それを改善する方法を探すきっかけとなった」のである 4。
これは、複雑なデータ分析の問題ではない。注意の集中とフィードバックの問題である。測定は特定の活動に注意を集中させ、日々の数値は即時的で単純なフィードバックループを提供する。このループが、進歩と達成を求める人間の自然な欲求を引き起こすのである。これは、測定イニシアチブから得られる最も重要な成果の一部が、その後の複雑な戦略よりも、初期の「観察者効果」から生まれる可能性を示唆している。
経営者にとって、これは、シンプルで目に見え、個人的に関連性のある指標が、より大きなパフォーマンス管理システムに統合される前でさえ、強力な動機付けツールとなり得ることを意味する。
第3章 適用のためのフレームワーク:測定を実践に制度化する
この章では、この原則が確立された経営フレームワークを通じてどのように運用され、単純なアイデアが体系的なプロセスへと転換されるかを詳述する。
3.1 KPI(重要業績評価指標):戦略を行動に変換する
KPIは、測定の原則を適用するための主要なツールである。KPIは、戦略的目標(KGI:重要目標達成指標)に対するパフォーマンスを評価するために用いられる、定量化可能な指標として定義される 1。
そのプロセスは、まず高次の目標(KGI、例:「年間売上を20%増加させる」)を設定し、その達成に不可欠な重要成功要因(CSF、例:「新規顧客獲得を増やす」)を特定し、そしてそれらの要因に対する具体的で測定可能なKPI(例:「リードから顧客への転換率」「顧客獲得単価」)を定義することからなる 36。
KPIは測定可能な目標の連鎖(カスケード)を創出し、日々の活動(KPIによって測定される)が組織の最高レベルの目標(KGI)に直接結びついていることを保証する。
3.2 PDCAサイクル:改善のエンジンとしての測定
しばしばデミングと関連付けられるPDCAサイクルは、継続的改善のためのフレームワークである。その中の「C(Check:評価)」の段階は、明確に測定と評価に関するものである 38。
この段階では、「D(Do:実行)」の段階の結果が測定され、「P(Plan:計画)」の段階で設定された目標と比較される。「何が機能し、何が機能しなかったか」の分析が、「A(Act:改善)」の段階での行動を方向づけ、改善を可能にする 38。
PDCAサイクルは、測定を動的なプロセスにおける反復的かつ不可欠なステップとして制度化する。それは一度きりの測定ではなく、仮説(Plan)、実験(Do)、測定(Check)、そして学習(Act)の継続的なループなのである。
3.3 SMARTの法則:目標設定に測定を組み込む
SMARTの法則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性、Time-bound:期限付き)は、効果的な目標を設定するために広く用いられる手法である 44。
「M(Measurable:測定可能)」は、この原則を直接的に組み込んでいる。目標が達成されたかどうかを判断するための明確で定量化可能な方法がなければ、その目標は適切に設定されたとは見なされない。これにより、「顧客満足度を向上させる」といった抽象的な願望は、「ネットプロモータースコアを40から50に引き上げる」といった具体的なターゲットへと強制的に変換される 44。
SMARTの法則は、目標設定の段階で測定を交渉の余地のない必須項目とする。これにより、曖昧で実行不可能な目標が設定されるのを防ぎ、目標そのものに説明責任が組み込まれることを保証する。
表3.1 部門横断型KPI便覧
以下の表は、様々な部門におけるKPI設定の具体例を統合したものである。この表は、高次のビジネス目標(KGI)から、それを達成するための重要成功要因(CSF)を経て、具体的な行動レベルの指標(KPI)へと至る論理的な流れを示しており、戦略的な思考のテンプレートとして活用できる 36。
| 部門 | KGIの例(戦略目標) | CSF(重要成功要因) | KPIの例(プロセス指標) |
| 営業 | 年間売上15%増 | 新規顧客獲得数と平均契約額の増加 | – 月間新規リード獲得数 – リード顧客転換率 (%) – 平均顧客生涯価値 (LTV) – 営業サイクル期間 (日数) |
| マーケティング | 市場シェア5%拡大 | ブランド認知度向上とリードジェネレーション | – ウェブサイトへのユニーク訪問者数 – コンバージョン率 (CVR) (%) – 顧客獲得単価 (CPA) – SNSエンゲージメント率 |
| 製造 | 生産コスト10%削減 | オペレーション効率と品質の向上 | – 設備総合効率 (OEE) (%) – 生産ライン不良率 (%) – 納期遵守率 (%) – 労働災害度数率 |
| 人事 | 従業員離職率20%削減 | 従業員満足度と定着率の向上 | – 従業員ネットプロモータースコア (eNPS) – 新入社員90日後定着率 (%) – 欠員補充までの平均日数 – 従業員研修参加率 (%) |
| カスタマーサポート | 顧客満足度95%達成 | 応答時間と初回解決率の改善 | – 平均初回応答時間 (時間) – 初回コンタクト解決率 (%) – 顧客満足度スコア (CSAT) – ネットプロモータースコア (NPS) |
第4章 指標の圧政:測定が病となるとき
この章は本レポートの重要な転換点であり、測定の原則をナイーブに、あるいは過度に適用することの重大な危険性と意図せざる結果を探求する。
4.1 グッドハートの法則:「指標が目標になるとき、それは良い指標であることをやめる」
このセクションでは、社会科学と経済学における基本概念であるグッドハートの法則を紹介し、解説する 54。この法則を具体的に示す古典的な事例を以下に挙げる。
- ソビエトの釘工場: 生産量を「重量」で測定された工場は、巨大な一本の釘を生産し、「本数」で測定されると、無数の小さく使い物にならないピンを大量生産した 56。
- コールセンター: 「処理した電話の本数」で評価されたコールセンターでは、オペレーターが顧客を急いで電話から降ろそうとし、結果的に顧客満足度を破壊した 55。
- 教育現場: テストの点数で評価される学校は、批判的思考や創造性を犠牲にして「テストのための指導」に注力するようになった 55。
グッドハートの法則は、単純化された測定に潜む致命的な欠陥を明らかにしている。人々は、指標が本来表すべきであった根底にある目標を犠牲にしてでも、指標そのものを最適化しようとする。指標は目標の代理(プロキシ)となり、やがてその代理が目標そのものに取って代わってしまうのである。
4.2 意図せざる結果:恐怖の文化と停滞するイノベーション
測定への過度な依存は、従業員が実験や失敗を恐れる「恐怖の文化」を生み出す可能性がある。それは人々を管理し、格付けするための「経営装置」として利用され、ストレスと不安を生み出すことがある 58。
それは創造性とイノベーションを阻害する。容易に測定可能で短期的な成果のみが報われるのであれば、従業員は、その便益が不確実であったり長期的であったりするような、斬新なアイデアに対するリスクを取らなくなる 58。
また、望ましい結論を支持するデータだけを「つまみ食い(チェリーピッキング)」し、そうでない情報を無視する行動につながり、測定が本来もたらすべき客観性そのものを損なう 59。
さらに、測定されている事業分野のみが注目され、部門間の協力や長期的な研究開発といった、測定されていないが重要な側面が衰退するという、視野の狭窄を招く可能性もある 54。
グッドハートの法則は単なる外部リスクではなく、内部的な認知バイアスでもある。「測定可能性バイアス」 56 は、たとえ測定不可能な事柄(企業文化や顧客からの信頼など)が戦略的により重要であっても、経営者や組織が測定
できるものを自然と過大評価し、測定できないものを過小評価することを示す。問題は、人々が指標を操作することだけではない。指標が人々を操作することにあるのだ。
このバイアスは、そもそも指標を設定する経営者自身に影響を与える。彼らがコールセンターの応対時間を測定対象として選ぶのは、それが顧客サービスの最も重要な側面だからではなく、測定するのが最も容易だからである。彼らがコードの行数を測定するのは、それが品質を表すからではなく、定量化できるからである 60。
測定の容易さが認知的な近道(ショートカット)を生み出す。指標が明確で、客観的で、追跡しやすいため、それは「顧客の喜び」や「コードの洗練性」といった曖昧な概念よりも「現実的」で重要に感じられる。これにより、経営者は本質的に間違った事柄に焦点を当てるシステムを設計してしまう。
したがって、グッドハートの法則への対策は、単に「操作不可能な」指標を作成することだけでは不十分である。それは、経営陣が自らの認知バイアスと戦うための、意識的かつ戦略的な努力を要求する。指標の圧政が支配的になるのを防ぐために、たとえそれが不快で曖昧であっても、測定不可能なものを価値あるものとして積極的に議論し、評価するよう、自らと組織を強制しなければならないのである。
第5章 数字を超えて:測定不可能なものを管理する
この章では、定性的評価を統合する必要性を論じ、組織において最も重要な事柄は、しばしば最も定量化が困難なものであると主張する。
5.1 定性的要因の戦略的重要性
デミングの哲学は、この主張を直接的に裏付けている。彼は、従業員の「仕事への誇り」、仕事における喜び、職場における恐怖(の欠如)といった、「未知であり、知り得ない」要因を管理することの重要性を強調した 30。
現代のビジネスは、従業員の士気、心理的安全性、顧客からの信頼、ブランドの評判、組織文化といった定性的な概念の価値を認識している。これらは単一の数値で容易に捉えることはできないが、長期的な成功の重要な推進力である 29。
定量的な指標のみに焦点を当てることは、巨大な死角を生む。ある企業は、四半期の売上目標をすべて達成しながらも、その文化が有害なものとなり、翌年にはトップタレントの大量流出を招くかもしれない。数字は、崩壊の瞬間まで良く見え続けるのである。
5.2 定性的評価の方法論
定性的評価とは、データを見捨てることではなく、異なる種類のデータを受け入れることである。これには、構造化面接、顧客からのフィードバックセッション、ユーザー観察(ユーザビリティテスト)、そしてテキストデータ(レビュー、サポートチケット、アンケートの自由記述欄)の感情分析などが含まれる 29。
人事分野では、「定性評価」は業績評価の正式な一部であり、リーダーシップ、チームワーク、主体性、責任感といった、容易に定量化できない特性を評価するために用いられる 61。
これらの手法は、定量的データが示す「何が(what)」の背後にある「なぜ(why)」を提供する。KPIは顧客離反率が5%上昇したこと(「何が」)を示すかもしれない。元顧客への定性的なインタビューは、彼らが無礼なサポート担当者や分かりにくいインターフェースのために去ったこと(「なぜ」)を明らかにするかもしれない。
5.3 ケーススタディ:従業員満足度への統合的アプローチ
高い離職率に直面していたあるレストランチェーンは、従業員満足度調査を活用した。最初の調査は定量的で広範なものであった。その後の調査では、従業員のコメントの定性的な分析を用いて「より深く掘り下げた」 70。
この定量的・定性的な混合アプローチにより、「労働時間」「評価」「給与」といった具体的な問題点が特定された。これにより、未消化の有給休暇の買い取りや新しいコミュニケーションツールの導入といった、的を絞った介入が可能となった 70。
このケースは、混合アプローチの力を示している。定量調査は問題の存在とその規模を特定した。定性分析はその根本原因を診断し、効果的な解決策へと導いた。どちらか一方の手法だけでは、これほど効果的ではなかっただろう。
「定量的」と「定性的」の区別は、しばしば誤った二分法である。最も強力な洞察は、組織が定性的データを体系的に収集・分析されるべきリソースとして扱い、時にはそれを定量データに変換(テーマ化、スコアリング)してパターンを明らかにするときに生まれる。例えば、アンケートの自由記述コメントは、テキストマイニングを用いてキーワードの出現頻度を分析できる 71。
顧客レビューは、特定の属性について1から5のスケールで「スコアリング」することができる 63。この「定性的なものの定量化」というプロセスは、大規模なパターン認識を可能にする。これにより、収益を追跡するのと同じように、「感情スコア」を時系列で追跡することが可能になる。これは、定性的なフィードバックを逸話の集まりから、構造化されたデータセットへと変換する。
これにより、経営者は、例えば「配送時間に関する苦情」が前四半期に30%増加した、といった、非構造化テキストから導き出された具体的で実行可能な洞察を得ることができる。したがって、組織は定性分析を「ソフト」で純粋に直感的な実践と見なすべきではない。むしろ、財務データに適用するのと同じ厳密さでこのデータを処理するためのシステムと能力(例えば、感情分析のためのAIの活用 72)を構築すべきである。
究極の目標は、定量的と定性のいずれかを選択することではなく、両者が互いを豊かにし、説明し合う統一されたデータエコシステムを創造することにある。
第6章 インテリジェントな測定のための統合的フレームワーク
この最終章では、効果的かつ人間的な測定システムを構築するための、リーダー向けの実践的な原則とチェックリストを提供する。
6.1 原則1:指標ではなく、目的から始める(デミング流)
何かを測定する前に、まずシステムの「目的(aim)」を明確に定義すること。すべての指標は、長期的にその目的に向かってシステム全体を最適化するのに役立つかどうかで評価されなければならない 31。単に測定しやすいという理由だけで何かを測定することは避けるべきである。
6.2 原則2:バランスの取れたスコアカードを採用する(全体的視点)
単一の指標に決して依存しないこと。財務的成果、顧客満足度、内部プロセス、そして組織の学習と成長といった、パフォーマンスの異なる側面をカバーする、バランスの取れた指標群(古典的なバランススコアカードのアプローチ)を用いること。これには、定量的指標と定性的指標の意図的な組み合わせが含まれる 29。
6.3 原則3:指標を判断の武器ではなく、診断ツールとして扱う
指標が非難のためではなく、学習と診断のために使われる文化を育むこと。KPIの低下は、即座の処罰(「誰のせいだ?」)ではなく、協力的な探求(「システムで何が起こっているのか?」)の引き金となるべきである。これは、デミングの「恐怖の排除」という原則と一致する 30。
6.4 原則4:自己統制を通じて力を与える(ドラッカー流)
測定システムは、主として仕事を行う人々の利益のために設計すること。個人やチームが自らのパフォーマンスを評価し、調整を行うのに役立つリアルタイムのデータを提供すること。これは、自律性、習熟、そして説明責任を育み、ドラッカーがMBOに込めた本来のビジョンと一致する 11。
6.5 インテリジェントな測定を実践するためのチェックリスト
以下は、本レポートの分析を総括する、実践的なチェックリストである。
- 目的との整合性: 提案されている指標について、それが組織の核心的な目的を達成するのにどのように役立つかを明確に説明できるか?
- システムへの影響: この指標に焦点を当てることが、システムの他の部分に悪影響を及ぼす可能性を考慮したか?(例:スピードを重視することが品質を損なわないか?)
- バランス: この指標は、定量的および定性的な指標のバランスの取れたセットの一部か? 我々の主要な「測定不可能なもの」は何であり、それらにどのように注意を払っているか?
- 操作の可能性: この指標はどのように「操作(ゲーム化)」され得るか? それはどのような倒錯した行動を助長する可能性があるか?(グッドハートの法則のチェック)
- エンパワーメント: この指標は、仕事を行う人々に実行可能なフィードバックを提供するか、それとも純粋に経営報告のためのものか?
- 見直しの頻度: 指標に対するパフォーマンスだけでなく、指標そのものの妥当性を定期的に見直すプロセスがあるか? それは依然として重要なことを測定しているか?
引用文献
- 計測していないものはマネジメントできない – PdMとPOが知るべき重要性, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.pdmpo.com/you-cant-manage-what-you-dont-measure/
- 「測定できないものは改善できない」~見える化の力と経営への応用~|望月史郎 – note, 10月 5, 2025にアクセス、 https://note.com/shirowkun/n/n4546d60114a4
- If You Can’t Measure It, You Can’t Improve It | Lessons from Peter Drucker – GuavaBox, 10月 5, 2025にアクセス、 https://guavabox.com/if-you-cant-measure-it-you-cant-improve-it/
- “If You Can’t Measure It, You Can’t Improve It.” | Advisorpedia, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.advisorpedia.com/growth/if-you-cant-measure-it-you-cant-improve-it/
- You Can’t Manage What You Can’t Measure | Growthink, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.growthink.com/content/two-most-important-quotes-business
- www.mtrigger.com, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.mtrigger.com/you-cant-manage-what-you-dont-measure/#:~:text=The%20quote%20%E2%80%9CYou%20can’t,t%20much%20better%20than%20guessing.
- You Can’t Manage What You Don’t Measure – mTrigger, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.mtrigger.com/you-cant-manage-what-you-dont-measure/
- 測定できないサスティナビリティは、管理できない – NetApp, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.netapp.com/ja/blog/sustainability-netapp-bluexp-dashboard/
- Measuring, Managing & Mattering. Don’t let your Strategy be Guided by… – Roger Martin, 10月 5, 2025にアクセス、 https://rogermartin.medium.com/measuring-managing-mattering-6cda8a80f924
- 目標管理の効果的運用, 10月 5, 2025にアクセス、 https://n-seiryo.repo.nii.ac.jp/record/1192/files/D0712.pdf
- 誤解されたドラッカーの目標管理、その本質を探る – Globis学び放題, 10月 5, 2025にアクセス、 https://globis.jp/article/58049/
- 1.目標による管理とは – ナビゲート, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.navigate-inc.co.jp/labo/mbo/01_1.html
- よくある質問 – マネジメントの意味 目標管理編, 10月 5, 2025にアクセス、 https://topmanagement.co.jp/faq/2010/10/post-66.php
- MBOで見落とされる「Self-control」。自律で成り立つ真の目標管理 – SmartHR Mag., 10月 5, 2025にアクセス、 https://mag.smarthr.jp/hr-management/evaluation/mbo_genrigensoku/
- 【保存版】ドラッカーに学ぶ!現代ビジネスに役立つマネジメント理論ベスト10 – コトラ, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.kotora.jp/c/104951-2/
- ドラッカーによるマネジメントの定義とは|名言10選を紹介 | オンライン研修・人材育成 – Schoo, 10月 5, 2025にアクセス、 https://schoo.jp/biz/column/497
- ドラッカーのマネジメントとは? 名言や『基本と原則』についておすすめの本もまとめてを紹介, 10月 5, 2025にアクセス、 https://teamhackers.io/drucker-management/
- ドラッカーのマネジメントを要約|必要な5つの要素 – 識学総研, 10月 5, 2025にアクセス、 https://souken.shikigaku.jp/152/
- ドラッカーの理論から「マネジメント」を紐解く。基礎知識や必要なスキルを解説, 10月 5, 2025にアクセス、 https://management-dx.jp/management-drucker/
- ドラッカーのマネジメント論を解説!マネジメントの定義&コツもご紹介 – recog, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.recog.works/ja/news/detail/111
- ドラッカーのマネジメントとは?5つの基本と名言をわかりやすく解説 – イー・コミュニケーションズ, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.e-coms.co.jp/column/drucker_management_theory
- 第5回:非ITの人たちは意外とできない「測定→報告→改善」 | システム管理者の会ポータルサイト, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.sysadmingroup.jp/kh/p556/
- 「忙しさ」は業務を測定することで改善できる | チームの生産性をあげる。 – ダイヤモンド・オンライン, 10月 5, 2025にアクセス、 https://diamond.jp/articles/-/132762?page=2
- 測定しないものは、マネジメントできない~デミングの名言に学ぶシステム思考と継続的改善, 10月 5, 2025にアクセス、 https://hp-ps.com/business/deming-measurement-system-thinking/
- W. Edwards Deming | Research Starters – EBSCO, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.ebsco.com/research-starters/history/w-edwards-deming
- デミングの誤引用 – 一人学際, 10月 5, 2025にアクセス、 https://scrapbox.io/hitorigakusai/%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E8%AA%A4%E5%BC%95%E7%94%A8
- If You Can’t Measure It… – Stacey Barr, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.staceybarr.com/measure-up/if-you-cant-measure-it/
- Berenson on the fallacy of “If you can’t measure it, you can’t manage it” – PNHP, 10月 5, 2025にアクセス、 https://pnhp.org/news/berenson-on-the-fallacy-of-if-you-cant-measure-it-you-cant-manage-it/
- Myth: If You Can’t Measure It, You Can’t Manage It – The W. Edwards …, 10月 5, 2025にアクセス、 https://deming.org/myth-if-you-cant-measure-it-you-cant-manage-it/
- W. Edwards Deming: From Profound Knowledge to 14 Points for Management, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.juran.com/blog/w-edwards-deming-from-profound-knowledge-to-14-points-for-management/
- Dr. W. Edwards Deming and Profound Knowledge – Part 1 – SPC for Excel, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.spcforexcel.com/knowledge/dr-w-edwards-deming/profound-knowledge-part-1/
- W. Edwards Deming – Wikipedia, 10月 5, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
- Deming’s 14 Points | Lean UTHSC | Business Productivity Solutions | Information Technology Services (ITS), 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.uthsc.edu/its/business-productivity-solutions/lean-uthsc/deming.php
- 「計測なくして改善なし」 ドラッカーの名言から学ぶ受験戦略 – 現論会, 10月 5, 2025にアクセス、 https://genronkai.com/utsunomiya/uncategorized/85/
- If you can’t measure it, you can’t improve it – Afropick, 10月 5, 2025にアクセス、 https://pick-afro.com/startup/if-you-cant-measure-it-you-cant-improve-it/
- KPIとは?具体例付きで、意味や設定方法をわかりやすく解説! – BowNow, 10月 5, 2025にアクセス、 https://bow-now.jp/media/column/kpi/
- 【事例あり】KPIを使った目標設定例3選!手順やポイントを解説 | 人事評価を科学するヒョーカラボ, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.seagreen.co.jp/blog/5152
- PDCAサイクルの失敗事例から学ぶ!回し方のポイントとは? | ダイレクトマーケティングラボ, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.ricoh.co.jp/magazines/direct-marketing/column/g00061/
- PDCAサイクルとは?メリットと成果を高めるポイントを解説 – Slack, 10月 5, 2025にアクセス、 https://slack.com/intl/ja-jp/blog/transformation/how-can-we-successfully-implement-the-pdca-cycle
- PDCAサイクルとは?メリットや目的、古いと言われる理由を簡単に解説 – Salesforce, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.salesforce.com/jp/blog/what-is-pdca-cycle/
- PDCAサイクルを実践して 生産性を高めよう – 厚生労働省, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/000812225.pdf
- PDCAサイクルとは?4つのステップやメリット・デメリット、成功させるコツを解説, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/blog/article-09.html
- PDCAサイクルを回すには適切なKPI設計が必要!4つの指標でO2Oマーケの成果を可視化, 10月 5, 2025にアクセス、 https://cinarra.co.jp/blog/143/
- SMARTの法則とは?具体例、目標設定のやり方、メリットを解説 – ハーモストレンド – HRMOS, 10月 5, 2025にアクセス、 https://hrmos.co/trend/talent-management/6016/
- SMARTの法則とは? 目標設定の意味・メリット・具体例を解説 – カオナビ人事用語集, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.kaonavi.jp/dictionary/smart-criteria/
- 【職種別】SMARTの法則を使った「仕事の目標例」を紹介 | リクナビNEXTジャーナル, 10月 5, 2025にアクセス、 https://next.rikunabi.com/journal/20220328_m01_s/
- SMARTとは?成果に繋がる目標設定の方法や、活用の注意点など徹底解説, 10月 5, 2025にアクセス、 https://bow-now.jp/media/column/smart/
- 【6ステップで分かる!】SMARTの法則とは? – 日報共有アプリgamba!, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.getgamba.com/guide/archives/47024/
- SMART 目標とは?設定方法とヒント、具体例を紹介 – Asana, 10月 5, 2025にアクセス、 https://asana.com/ja/resources/smart-goals
- KPI目標設定の具体例【業種別・職種別】|手順やポイントも解説 – 経営管理 – Manageboard, 10月 5, 2025にアクセス、 https://service.manageboard.jp/blog/20250526/
- KPIとは?設定する意義や設定方法、活用事例を紹介 – 三井住友銀行, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.smbc.co.jp/hojin/magazine/sales/about-kpi.html
- 営業のKPIとは?KGIとの違いや項目例一覧、立て方を詳しく解説 – Salesforce, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.salesforce.com/jp/blog/jp-sales-kpi/
- KPIの具体例とは? 営業やマーケティング、システム開発等の観点から解説 – Tableau, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.tableau.com/ja-jp/learn/articles/kpi-example-and-merit
- IF YOU CAN’T MEASURE IT; YOU CAN’T MANAGE IT, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.allanmucerino.com/post/if-you-can-t-measure-it-you-can-t-manage-it
- グッドハートの法則 Goodhart’s Law – UX DAYS TOKYO, 10月 5, 2025にアクセス、 https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/goodharts-law/
- 間違った指標で改善進める現象って名前なんだっけ?なんか有名な事例話もあったような – note, 10月 5, 2025にアクセス、 https://note.com/iepyon/n/nb0becd9c11f5
- グッドハートの法則|総務部総務課 マモたろう – note, 10月 5, 2025にアクセス、 https://note.com/nashikuzushi5/n/n17b4026136e0
- “If you can’t measure it, you can’t manage it.” But we can. Can’t we? – Neil Usher – Medium, 10月 5, 2025にアクセス、 https://workessence.medium.com/if-you-cant-measure-it-you-can-t-manage-it-but-we-can-can-t-we-e49479e4bf6c
- An ode to the KPI: If you can’t measure it, you can’t improve it | Proove Intelligence, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.prooveintelligence.com/blog/an-ode-to-the-kpi-if-you-cant-measure-it-you-cant-improve-it/
- グッドハートの法則を、あなたの日常会話にどう適用できますか? : r/socialskills – Reddit, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/socialskills/comments/16dpwhq/how_can_you_apply_goodharts_law_into_your/?tl=ja
- 定性評価とは数値以外の評価方法!定量評価との違いや具体例・導入時の注意点を解説, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.ashita-team.com/jinji-online/organization/10080
- 定性データとは?数値にできない情報の本当の価値と活用法 | GLOBIS学び放題×知見録, 10月 5, 2025にアクセス、 https://globis.jp/article/dic_vlgfu8kysoy/
- 定量化とは?ビジネスにおける意味と定性化との違いをわかりやすく解説 – Salesforce, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.salesforce.com/jp/blog/jp-what-is-quantification/
- 定量分析・定性分析とは?具体的な手法や組み合わせる方法も解説 | 株式会社ニジボックス, 10月 5, 2025にアクセス、 https://blog.nijibox.jp/article/quantitative_quantification/
- 定性評価とは?人事評価における方法や定量評価との違い、注意点を解説|One人事, 10月 5, 2025にアクセス、 https://onehr.jp/column/human-resources/qualitative-evaluation/
- www.pa-consul.co.jp, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/TalentManagementLab/qualitative-assessment/#:~:text=%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AF%E3%80%81%E6%95%B0%E5%80%A4%E5%8C%96%E3%81%97,%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82
- 定性評価とは|定量評価との違い、人事評価に導入する方法やメリット、注意点, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/TalentManagementLab/qualitative-assessment/
- 定性評価とは?具体例やメリット、評価方法・定量評価との違いを解説 – Chatwork, 10月 5, 2025にアクセス、 https://go.chatwork.com/ja/column/work_evolution/work-evolution-268.html
- 【具体例あり】定量目標と定性目標の設定ポイントを職種&社歴別に解説, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.tcpartners.co.jp/blog/blog-3370/
- 従業員満足度(ES)向上国内事例をご紹介!有名チェーン店は離職を防ぐために何をしているのか? | 株式会社エモーションテック – Emotion Tech, 10月 5, 2025にアクセス、 https://emotion-tech.co.jp/column/2019/es_case_japan/
- 従業員満足度調査(ES調査)とは?目的や具体的な方法を解説! – モチベーションクラウド, 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.motivation-cloud.com/hr2048/c220
- AIによる定性的データ分析 | MB Strategy 経営戦略 – note, 10月 5, 2025にアクセス、 https://note.com/mb_strategy/n/ne97f56cc93d6
- プロジェクト管理に利用できる知識/法則|Sky Tech Blog(スカイ テック ブログ), 10月 5, 2025にアクセス、 https://www.skygroup.jp/tech-blog/article/988/
- 指標はハックされる〜グッドハートの法則 – sa2taka blog, 10月 5, 2025にアクセス、 https://blog.sa2taka.com/til/2023-10-11-goodhart/
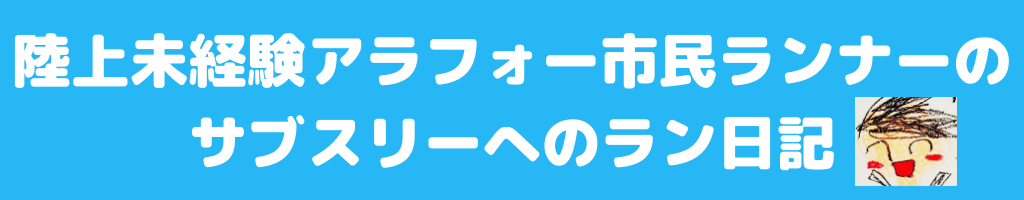

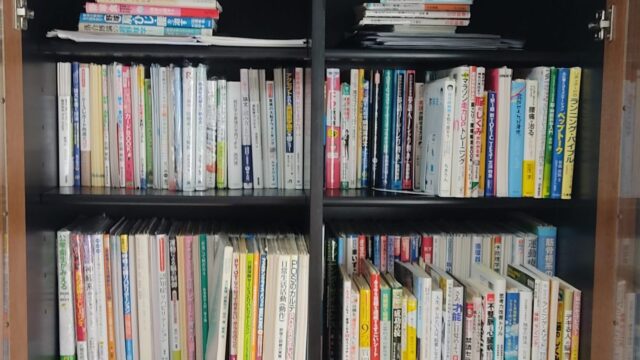
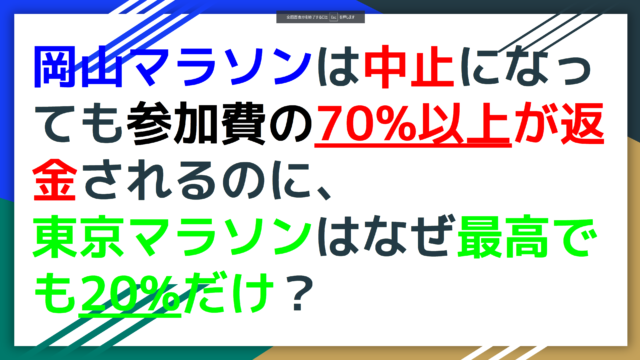
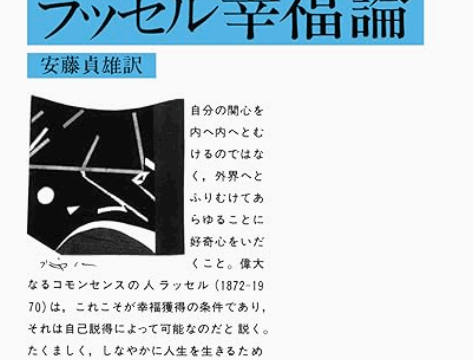
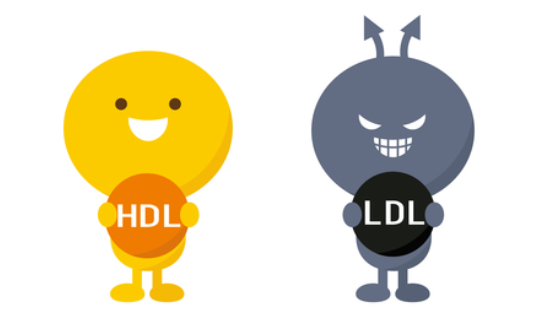
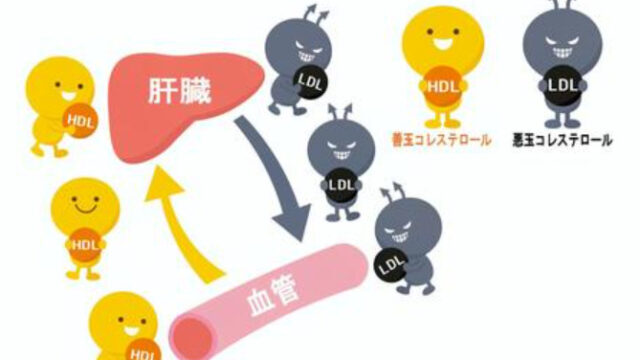

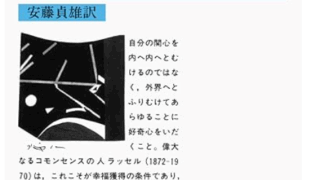





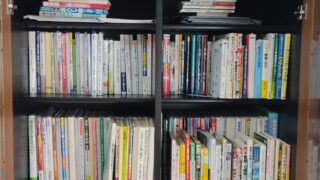

はじめまして。 とても興味をひかれました! ふだん改造ビーチサンダルやlun…
ありがとうございます。嬉しいです みちさんが保存療法でよくなることを願っています…
経過良好で安心しました^_^ やはりリハビリが大事なのですね。 術後の記事、…